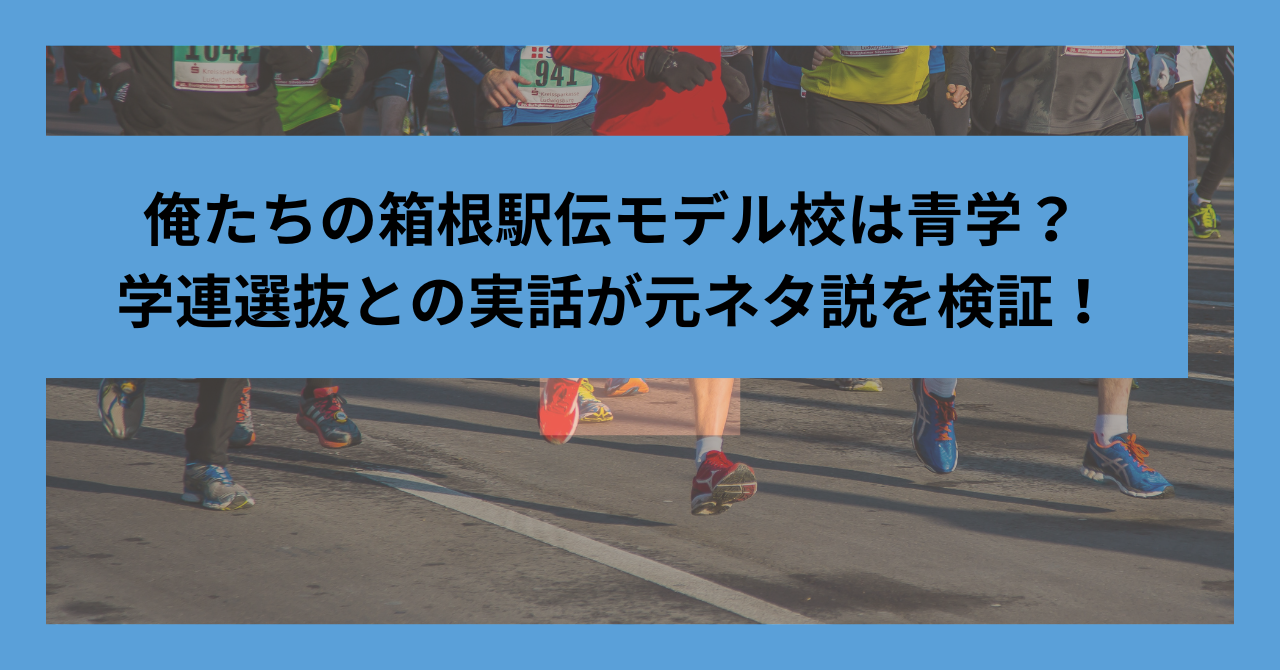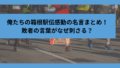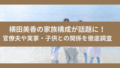2024年に刊行された池井戸潤さんの小説『俺たちの箱根駅伝』が、スポーツ小説として異例の注目を集めています。
舞台は箱根駅伝。しかも、主役は予選落ちした大学の選手たちが集まる“学生連合チーム”という異色の設定です。
読者の間では「モデル校は青山学院大学では?」という声が急増中。さらに、2008年に実在した“学連選抜”の奇跡とも重なる内容に、「これは実話が元ネタでは?」と噂されています。
この記事では、小説の内容と実在エピソードを比較しながら、“モデル校”の正体を徹底検証。
この記事でわかること
- 『俺たちの箱根駅伝』のモデル校は本当に青山学院大学なのか?
- 学連選抜チームの実在エピソードとの共通点
- 明治大・東洋大など他大学との比較と考察
- 原晋監督と作中キャラのシンクロぶり
- 小説に込められた“敗者の美学”と時代背景
俺たちの箱根駅伝モデル校は青学?
2024年に発表された池井戸潤さんの新作小説『俺たちの箱根駅伝』は、スポーツ青春ドラマでありながら、まるで実在の駅伝チームを追体験しているかのようなリアルさで話題になっています。
その中でも特に注目されているのが「この作品のモデル校はどこなのか?」という点です。
多くの読者や駅伝ファンの間で最有力とされているのが青山学院大学。
特に、学生連合チームを率いる“元会社員”の監督や、寄せ集めの選手が短期間で結束して奇跡を起こすという展開に、青学が過去に成し遂げた“ある快挙”を思い出す人は多いはず。
果たしてこの推測は的を射ているのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。
青学の挑戦と改革がドラマのテーマと一致?
青山学院大学といえば、今でこそ箱根駅伝の常連上位校ですが、2000年代初頭は無名校の一つでした。
その転機となったのが、2004年に原晋監督が就任したことです。
元は中国電力の営業マンだったという異色の経歴を持つ原監督は、伝統や慣習にとらわれず、科学的なトレーニングや選手主体のチームづくりを進めました。
この“挑戦と改革”の姿勢は、小説『俺たちの箱根駅伝』に登場する新米監督・甲斐の描き方と非常に似ています。
甲斐もまた会社員から指導者に転身し、型破りな練習方法や選手同士の対話を重視する姿勢で、バラバラだった連合チームを一つにまとめていきます。
読者からは「まるで青学の変革期を見ているようだった」との声もあり、池井戸さんが意図的に“原監督イズム”を重ねているように感じられます。
原晋監督とドラマの監督の共通点は?
作中の甲斐監督と、現実の原晋監督にはいくつかの明確な共通点が見られます。
-
元会社員という異色のキャリア
-
駅伝未経験ながら「選手の主体性」を重視
-
短期間でチームをまとめあげる手腕
-
メディアにも積極的に登場し、“見せる駅伝”を意識した発信
実際、池井戸潤さんは原監督への取材も行っており、作品内でも「君たちはどうしたいんだ?」という問いかけが、原監督の実際の指導フレーズとそっくりなのも注目ポイントです。
特に2008年の学連選抜で監督を務めた経験は、まさに本作の核心に通じています。
青学黄金時代とドラマの描写の比較
青山学院大学は2015年から箱根駅伝で5度の総合優勝を成し遂げ、“黄金時代”と呼ばれる快進撃を見せました。
この時期の青学は、単なる強豪ではなく「一人ひとりが自分の考えで動ける」「勝っても奢らず、負けても前を向ける」チーム文化を築いていたことが大きな特徴です。
これは、『俺たちの箱根駅伝』に登場する明誠学院大学連合チームの描写と見事に重なります。
一人ひとりが「ただ速い」だけでなく、「自分の役割を理解して走る」姿は、まさに青学のスタイルそのもの。
そして、“負け続けたチームが信じ合うことで変わる”という物語の構造自体、原監督率いる青学の軌跡をなぞるような内容になっているのです。
俺たちの箱根駅伝モデルは学連選抜との実話が元ネタ説を検証!
青山学院大学との関連が話題になっている一方で、この小説にはもう一つの“リアルな元ネタ”が存在します。
それが「学連選抜チーム」の実在エピソードです。
作中では、予選会で敗れた明誠学院大学の選手・青葉隼人さんが、他大学の選手たちと共に“学生連合チーム”を組んで本選に挑みます。
この構図は、実際の箱根駅伝に存在した「関東学生陸上競技連合選抜チーム(通称:学連選抜)」とそっくり。
特に2008年大会のエピソードは、本作のストーリー展開に強く影響を与えていると考えられています。
2008年学連選抜チームの快挙とは?
2008年の箱根駅伝で、予選会敗退校の精鋭を集めた学連選抜チームが、大方の予想を覆す快走を見せました。
チームを率いたのは、当時青山学院大学の監督に就任して5年目だった原晋監督。
選手たちは「JKH SMART」という愛称で団結し、以下のような奇跡を起こします。
-
往路5区の山登り区間で驚異の区間賞獲得
-
全体でシード権相当の順位に食い込む(参考記録ながら“総合4位相当”)
-
無名選手の成長と仲間意識の芽生えが話題に
この快挙は「伝説の学連選抜」と語り継がれ、原監督の指導力と、選手たちの自主性が大きな称賛を浴びました。
小説で描かれる、“数週間の合宿で信頼を築いていくプロセス”や、“本選での一体感の爆発”は、まさにこの年の学連選抜の姿に重なります。
選抜チームが注目された過去の大会
学連選抜チームは1963年から制度として導入され、予選敗退校の中から個人タイムが優秀な選手を選抜して、本選出場が認められる仕組みです。
いくつかの年で印象的な活躍を見せてきましたが、特に話題になったのが以下の年です。
-
1996年大会:早稲田大学の補欠選手が中心となり注目
-
2008年大会:原晋監督率いる選抜チームが“歴代最強”の評価を受ける
-
2012年以降:制度の意義が再評価される一方、成績面で苦戦
しかし2020年代に入ってからは“実力差”や“安全管理上の懸念”が議論となり、第100回大会(2024年)では記念大会の特別措置として編成が見送られました。
一方で、2025年6月19日の関東学生陸上競技連盟発表により、2026年大会(第102回)から編成方法が大幅に変更され、制度は継続・強化されることが決定しています。
新ルールでは、予選会11位~20位の大学から各1名(計10名)のチーム枠と、21位以下の大学から個人成績上位6名(各校1名)の個人枠を設け、出走経験1回までの選手も選考対象に含め、再チャレンジの機会を拡大します。
この改革のタイミングが、まさに「今、学生連合チームを描く意義」を物語に深みとして与えています。
予選落ちの選手たちが新たな形で箱根路に挑む姿は、敗者の再起とチームの多様性を象徴し、池井戸潤さんの小説が現実の変革と響き合う機会を生み出しているのです。
ドラマ内チーム構成と学連選抜の共通点
小説に登場する“連合チーム”は、予選で敗退した大学の主将やエース級を中心に編成されます。
作中では以下のような特徴が描かれています。
-
1万メートル30分切りの記録を持つ選手が基準
-
直前の合宿でリレーバトンの精度を徹底強化
-
個々の実力は高いが、チームとしての連携はゼロから構築
これはまさに、学連選抜チームの選考・編成そのもの。
さらに、作中では“参考記録でしかない”ことに悔しさを感じる描写や、“シード校に食らいつく走り”に注目が集まる展開など、実際の学連選抜の心理と現実をよく表しています。
こうした点からも、『俺たちの箱根駅伝』は単なる創作ではなく、実在した制度や記憶をもとに丁寧に組み立てられていることがわかります。
青学・学連選抜以外にもモデルがある?
『俺たちの箱根駅伝』は、青山学院大学や学連選抜のエピソードがモデルとして有力視されていますが、それ以外にも参考にされたと見られる大学や実在人物が存在します。
池井戸潤さんは「特定の大学をモデルにしたわけではない」とインタビューで語っているものの、細かい設定や人物像には、いくつかの大学の実例が合成されていると考えられます。
ここでは、青学・学連選抜“以外”のモデル候補や、登場人物との対応関係を見ていきましょう。
明治大学、東洋大学などとの比較
まず挙げられるのが、明治大学です。
明治大学は過去に何度も学連選抜に選手を送り出しており、特に2008年の選抜チームにも複数の選手が参加していました。
以下の点で、作中の連合チームに影響を与えたと考えられます。
-
“シード圏外に沈むも選抜選手が活躍”という現実の構図
-
歴史ある伝統校のプライドと、現実のギャップを背負う姿
-
複数の大学から選手が集まる“寄せ集め感”のリアリティ
また、東洋大学についても、山登り区間の強さや「山の神」の存在が、作中の“第5区ヒーロー”の描写に影響しているという見方があります。
東洋大学は、箱根駅伝の山岳区間で“逆転劇”を演じた実績があり、「山で勝負が決まる」という戦略が、小説のレース展開に重なります。
その他、中央学院大学や帝京大学など、安定した予選突破ながら本選では苦戦するタイプの大学も、キャラクター設定のモデルとして参考にされている可能性があります。
ドラマ登場人物と実在選手の共通点
作中には、多くの個性豊かな選手や中継スタッフが登場しますが、彼らの描かれ方にも実在選手の影が見え隠れします。
例えば、
-
キャプテン・青葉隼人さん:メンバーを鼓舞しながら、自らも成績に苦しむ姿は、2008年の学連選抜の主将(國學院大の選手)と酷似
-
5区担当の“山男”キャラ:東洋大学の柏原竜二さんを想起させるような、圧巻の登りと精神力が描写される
-
サポート役のマネージャー:青山学院のマネジメントスタッフの運営力がモデルとの声も
一方で、大日テレビのディレクターや実況アナウンサーの描写もリアルそのもので、実在の中継現場を取材して得た情報が活きていることが分かります。
そのため、“モデル=誰か一人”ではなく、複数の大学・人物を合成しながらフィクションとして昇華した構成になっていると見られます。
池井戸潤の取材・創作背景とは
『半沢直樹』や『下町ロケット』など、ビジネスや技術の裏側をリアルに描くことで定評のある池井戸潤さん。
今回の『俺たちの箱根駅伝』では、スポーツ、しかも大学駅伝という分野に挑戦しましたが、その緻密な取材力と構成力は健在です。
読者からも「ここまで箱根駅伝の内部を再現できるとは」「テレビ中継の裏側に感動した」という声が多く寄せられています。
では、池井戸潤さんがこの作品を通じて何を描こうとしたのか。過去作との共通点や、制作サイドの意図を掘り下げてみましょう。
下町ロケットとの共通テーマ
一見ジャンルが異なるように見える『下町ロケット』と『俺たちの箱根駅伝』ですが、実は以下のようなテーマで深く繋がっています。
-
“寄せ集めチーム”が目標に向かって成長する過程
-
リーダーの言葉が人を動かし、組織を変えていく力
-
主役は“光の当たらない場所”で奮闘する人々
-
技術や走力以上に、“想い”や“信頼”が勝敗を分ける
『下町ロケット』では中小企業の技術者たちが大企業に挑み、『俺たちの箱根駅伝』では無名の学生たちが箱根本選の上位を目指します。
どちらにも共通しているのは、「報われない努力を、最後に報われる形に変えてみせる」という池井戸さんらしい逆転の美学です。
制作スタッフや脚本から見える意図
2026年に日本テレビ系で連続ドラマ化が決定した本作では、脚本を『アンチヒーロー』などの鈴木すみれさん、松田裕子さんが手がけ、演出は猪股隆一さん、山田信義さんらが担当。
プロデューサー陣には小田玲奈さん、藤澤季世子さん、大井章生さんらが名を連ね、関東学生陸上競技連盟の全面協力のもとで制作が進んでいます。
日本テレビは1987年以来、箱根駅伝を生中継してきた局として、原作のリアリティを活かした“前人未踏の映像プロジェクト”を標榜しており、キャストの詳細発表も今後の注目点です。
制作側は「一度は敗れた者たちの熱き青春」を強調し、「単なるスポーツ根性ものではなく、“現代に響く青春群像劇”を描きたい」との意図を明言。
以下のような方針が読み取れます。
- “仲間と信じ合うこと”を現代の若者に伝えたい
- スポーツだけでなく、舞台裏の苦労や奮闘も丁寧に描く
- 原作の緻密さを損なわずに“熱さ”をプラスする演出を意識
池井戸潤さん自身も、連載開始前のインタビューで「現場を取材して初めて見えた“箱根のドラマ”があった」と語っており、走る側だけでなく、支える側のストーリーにこそ重きを置いた作品づくりが行われています。
実際、執筆には十余年の取材を重ね、日本テレビの副調整室を訪れて中継の雰囲気を肌で感じたり、学生記者との対話で創作哲学を深めたりするなど、徹底したリアリティ追求が光ります。
池井戸さんは「本気で戦わないレースからは何も得られない」とも述べ、取材の過程で体調を崩すほどの没入感を明かしています。
箱根駅伝敗者の美学とは?ドラマが伝えたかったこと
『俺たちの箱根駅伝』は、ただのスポーツ青春小説ではありません。
本作が描く最大のテーマの一つは、“敗者”とされる立場の選手たちが、どのようにして光を放つ存在へと変わっていくかという物語です。
特に、予選落ちという現実を受け止めながらも、学連選抜として箱根本選に出場する選手たちの姿には、“敗者の美学”とも言うべき価値が込められています。
箱根駅伝という「勝者がすべて」の舞台で、なぜあえて“報われない努力”を描くのか。その背景と、現代社会へのメッセージを紐解いていきます。
学連選抜の「報われない努力」が描かれる理由
学連選抜は、予選会で敗れた大学から選ばれた選手たちによって構成されます。
どれだけ走力があっても、成績は参考記録にしかなりませんし、シード権を獲得することもできません。
それでも、彼らは走ります。声援を背に、仲間の想いを背負って。
この“報われない努力”を描くことは、以下のような意味を持っています。
-
結果ではなく、過程にこそ価値があるというメッセージ
-
目立たない立場でも、全力を尽くす姿の美しさ
-
「勝者」だけが語られる社会に対するアンチテーゼ
池井戸潤さんはこのテーマを、小説全体にわたって丁寧に描いています。
走り切った選手が「何も残らなかった」と涙する場面、チームが一体になった時の“無名選手の輝き”など、読者の心を揺さぶるシーンが随所にちりばめられています。
なぜ今このテーマなのか?共感を呼ぶ背景
“報われない努力”というテーマが今の時代に響くのは、次のような社会背景があるからです。
-
成果主義やSNS評価社会への違和感
-
若者世代が感じる「評価されにくい頑張り」への共感
-
コロナ禍を経た“失われた時間”の回復としての再出発
特に、大学生や20代前後の読者には、「努力が目に見える形で報われなくても、何かをやり遂げた経験には価値がある」というメッセージが響きやすいでしょう。
この作品は、ただの勝利物語ではなく、“努力を重ねたすべての人たち”を讃える物語。
それが『俺たちの箱根駅伝』がこれほどまでに多くの人の心を掴んでいる理由のひとつです。