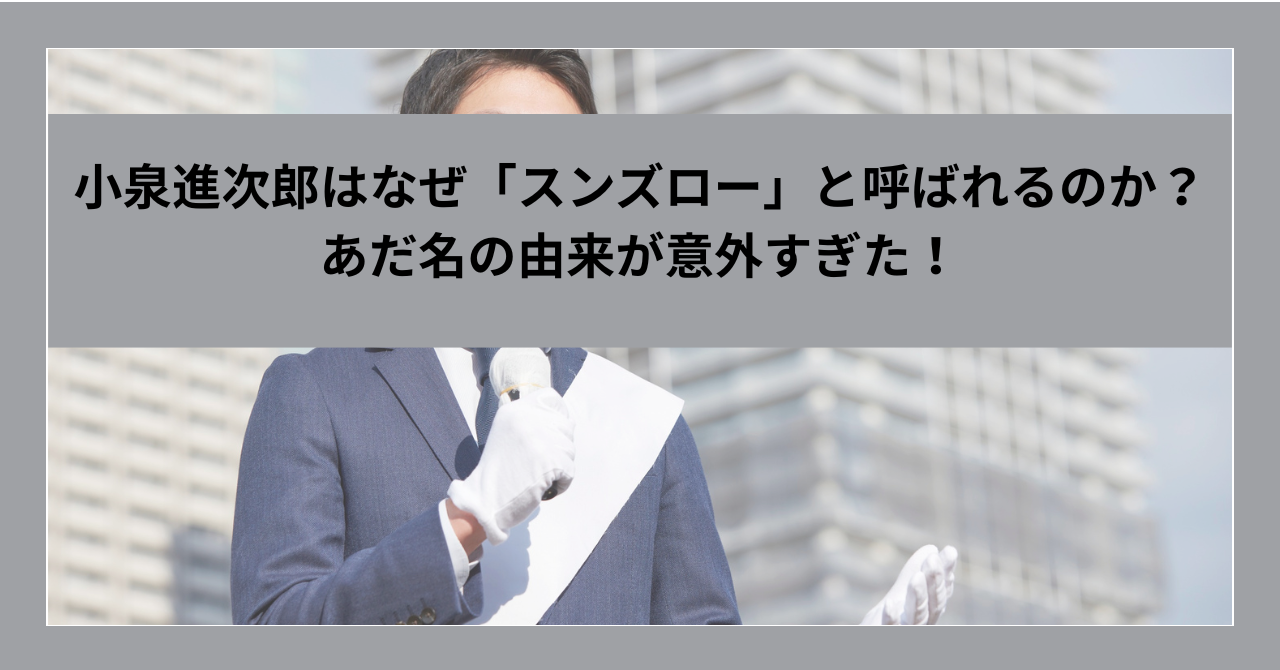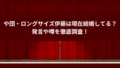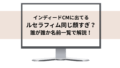SNSやネット掲示板でふと目にする「スンズロー」という不思議な名前。
一体誰のこと?と思ったら、なんとあの小泉進次郎さんのことだった…!
でも、なぜ「スンズロー」? どこからそんな名前が出てきたの?
そんな疑問を抱いた人のために、この記事ではこのあだ名の意外すぎる由来や広まった背景を徹底解説。
本人の発言から始まった可能性や、「進次郎構文」と呼ばれるユニークな言葉遣いとの関係、そしてネット文化との不思議な融合まで。
読んだらきっと「なるほど、スンズローってそういうことか!」とスッキリできるはずです。
この記事でわかること
小泉進次郎さんが「スンズロー」と呼ばれるようになった由来
ネットでの呼ばれ方と広まった時期
本人が関与していたというエピソードの真偽
「進次郎構文」とのつながりとミーム化の流れ
SNSでの受け止め方や使われ方のニュアンス
小泉進次郎はなぜ「スンズロー」と呼ばれるのか?
小泉進次郎さんにまつわるあだ名「スンズロー」。
一見、意味不明にも思えるこの呼び名ですが、実はネット上ではすでに一定の認知度を持つ言葉として流通しています。
しかも、メディア記事でも使われたことがあるんです。
たとえば日刊スポーツの記事では、落語家・立川談四楼さんが小泉進次郎さんに言及する際にこう語っています。
「スンズローは早かった。高いコンバインはリースでって、そりゃ農家は怒るよ」
引用元:日刊スポーツ|2025年6月18日配信
このように、「スンズロー」はネットスラングにとどまらず、文化人の発言としても記録されており、一定の認識を持たれているあだ名なのです。
突然見かける「スンズロー」という言葉の正体
「スンズロー」は、小泉進次郎さんのファーストネーム「進次郎」をユニークに変形させたあだ名です。
親しみを込めたような語感もあれば、やや風刺的・皮肉的なニュアンスも感じられる、絶妙なラインを突いた呼び名。
SNSや掲示板、さらにはニュースのコメント欄などでも使われており、「進次郎構文」と呼ばれる言葉とセットで語られることも多いです。
これはつまり、「発言のわかりにくさ」や「意味のなさ」をいじりながらも、キャラクターとして親しまれているということでもあります。
いつから広まった?ネットミームとしての登場時期
「スンズロー」が目立つようになったのは、2019年に小泉進次郎さんが環境大臣に就任し、会見などで注目され始めた頃です。
とりわけ、彼の発言がたびたび「進次郎構文」として取り上げられるようになると、そのキャラ性を補完するかたちで「スンズロー」というあだ名も広まっていきました。
進次郎構文の社会的認知については、毎日新聞の記事でもこう紹介されています。
「これまでの発言は、独特の言い回しから『進次郎構文』と呼ばれた」
引用元::毎日新聞|2024年9月10日配信
このように、「スンズロー」というあだ名は、言葉の使い方とイメージの両方がネットで合成されたミーム的表現だといえます。
小泉進次郎本人の発言が由来だった?
「スンズロー」というあだ名には、実は小泉進次郎さん自身が関わっているという説があります。
「勝手にネットでつけられた」だけでなく、本人がどこかで使った?もしくは、地域の人がそう呼んだ?
そんなエピソードが語られるようになったことで、ネタから“キャラ付け”へと変化していったのです。
岩手での講演エピソードがきっかけ
このあだ名の誕生について語られることが多いのが、2013年1月に小泉進次郎さんが岩手県大船渡市で行った講演でのエピソードです。
当時、会場に集まった地元の高齢者と交流する中で、小泉進次郎さんは冗談まじりにこう発言したといわれています。
「さっきおばあちゃんに名前を変えてもらいました。今日から小泉すんずろうです!」
このユーモアあふれる自己紹介が、後にネット上で「スンズロー」としてネタ化されたという説が濃厚なんです。
あくまで伝聞やまとめサイトを通じて広まった話ではありますが、本人発信の“ネタ名乗り”であるなら、それが親しみを込めて広がっていったのも納得ですよね。
このエピソードが本当なら、「スンズロー」はただのネットのいじりではなく、小泉進次郎さんの柔らかい人柄を象徴するワードとも言えそうです。
地域の訛り?「すんずろう」の語感に隠された背景
もうひとつ語られるのが、「すんずろう」という言い回しが、岩手など東北地方の訛りやイントネーションに由来するという説です。
進次郎(しんじろう)という名前が、地元の高齢者の訛りで「すんずろう」風に聞こえたというのは、方言が豊かな地域ではよくある話。
親しみを込めて名前を崩して呼ぶのは、地方文化の中ではごく自然なことです。
この「すんずろう」が、小泉進次郎さんにとって「おばあちゃんが呼んだ名前」として記憶に残り、そのまま講演などでも使われたとすれば、背景には言語的な愛嬌があるともいえます。
つまり、ネットで使われる「スンズロー」は、実は地域の温かみや交流の中から生まれた言葉だった…という可能性もあるんですね。
小泉進次郎の発言スタイルとは
小泉進次郎さんは、政治家としては珍しく比喩や抽象表現を多用し、「何となく耳障りはいいけど、具体性に欠ける」と感じさせる発言スタイルで知られています。
以下の独特な言い回しがSNSなどで話題になりました。
進次郎構文と名付けられる
毎日新聞の記事ではその特徴が次のように説明されています。
「これまでの発言は、独特の言い回しから『進次郎構文』と呼ばれた」
引用元:毎日新聞|2024年9月10日配信
さらに代表的な発言例としては、この一言が知られています。
2019年の国連気候行動サミットの会見
「気候変動のような大きな問題に取り組むには、それは楽しくなければならず、クールでなければならない。それもセクシーでなければならない」
引用元:参議院 公式会議録
この“セクシー発言”は国内外で報道され、「言いたいことはなんとなく伝わるけど、結局何がセクシーなの?」と多くの議論を巻き起こしました。
また、ネットでは以下のように引用されることもあります。
進次郎構文の例がネタ
「誕生日なんですね。私も誕生日に生まれたんです」
引用元:ダイヤモンド・オンライン|2023年7月7日配信
これらの発言に共通しているのは、「意味よりも印象が優先される」「言葉のリズム感が強い」という特徴です。
まさにこのスタイルこそが、「スンズロー」というキャラ性がミーム化した背景にある、進次郎節の正体なのかもしれません。
まとめ
ここまで『小泉進次郎はなぜ「スンズロー」と呼ばれるのか?あだ名の由来が意外すぎた!』と題してお送りしました。
-
「スンズロー」はネットで定着したあだ名で、日刊スポーツなどニュース記事でも実際に使用されている
-
由来とされる講演発言は伝聞レベルでの流布が主だが、ネットでは有力な説として語られている
-
小泉進次郎さんの「進次郎構文」と呼ばれる発言スタイルは、毎日新聞など複数メディアが紹介している
-
国連気候サミットでの「セクシーでなければならない」という発言は、参議院の質問主意書にも正式に引用されている
-
SNSでは「スンズロー」が親しみと皮肉を込めた“キャラ呼び”として浸透し、ミーム化した存在になっている
「スンズロー」という呼び名は、ネットスラングの一種ではありながら、政治家の発言やパブリックイメージの反映として現代的な意味を持っています。
ネタと軽視するだけでは見落とす背景があり、時代の空気や人々の言語感覚が見えてくる。
そんな面白さと奥深さを感じられるミームとして、今後も語り継がれていくかもしれません。